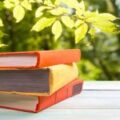離婚は、その後の人生設計に大きく関わる財産の問題を伴います。特に「財産分与」は、夫婦が協力して築き上げた財産を公平に分配するための重要な手続きです。
しかし、この財産分与を請求できる権利には、離婚後2年という厳格な時間的制約があります。この期限を過ぎてしまうと、本来得られるはずだった財産を受け取れなくなる可能性があります。離婚後の生活を安定させるためには、財産分与の請求権に関する正しい知識と、権利を失わないための計画的な行動が不可欠です。
本稿では、財産分与請求権の時効(正しくは「除斥期間」)の基本や、万が一期限が迫ったり、過ぎてしまったりした場合の対処法について、詳しく解説します。
1 財産分与の請求権の期限は離婚後2年
離婚のお悩み--離婚問題に強い弁護士に相談してみませんか?
初回相談は無料。電話 6:00–24:00で予約可。対面/Zoom、秘密厳守で対応します。
- 離婚問題に強い経験豊富な実力派弁護士が対応
- 1分単位で費用が“見える”(タイムチャージ制)だから安心
※ご相談内容により一部有料となる場合があります。
離婚後の財産分与を請求できる権利は、離婚が成立した時から2年で消滅します。
注意すべきなのは、この2年という期間が一般的な「消滅時効」ではなく「除斥期間(じょせききかん)」であるという点です。
「消滅時効」は権利を行使しない状態が一定期間続いた場合に権利が消滅する制度であり、完成を猶予させたり、更新(中断)させたりすることが可能です。
一方、「除斥期間」は、法律が定める権利の存続期間です。期間の経過によって当然に権利が消滅し、原則として中断や延長が認められません。
すなわち、財産分与の請求権は、相手に「財産を分けてください」と口頭や書面で伝えるだけでは、2年の期間経過を止めることはできません。権利を確定的に守るためには、2年以内に家庭裁判所へ「財産分与請求調停」を申し立てる必要があります。
この期間は、離婚届が受理された日、または裁判離婚の場合は判決が確定した日から進行します。あっという間に過ぎてしまうので、離婚後は速やかに行動を開始することが重要です。
2 調停・審判中に2年が経過した場合、権利は守られるのか?
「2年以内に調停を申し立てなければならないのは分かったけれど、話し合いが長引いて、調停の途中で2年が過ぎてしまったらどうなるの?」と不安に思われる方もいるでしょう。
しかし、離婚成立から2年以内に家庭裁判所へ財産分与請求調停(または審判)の申立てさえ行っていれば、その手続きの途中で2年が経過したとしても、権利は法的に保護されます。
裁判所が、申立てが2年の期間内に行われたことを確認しているため、最終的な結論が出るまでに時間がかかったとしても、申立て時点に遡って権利が保全されます。
したがって、相手との話し合いが難航し、2年の期限が迫っている場合には、躊躇することなく家庭裁判所での手続きを開始することが、権利を守るための最も確実な方法といえます。
3 2年経過後に財産分与を実現するための最終手段
万が一、離婚後2年の除斥期間が過ぎてしまった場合、法的な強制力をもって財産分与を請求する権利は原則として失われます。しかし、限定的ではあるものの、財産分与を実現するためのいくつかの方法が残されています。
3-1 期限後でも請求が可能な任意の話し合いとは?
除斥期間が経過すると、相手方には財産分与に応じる法的な義務はなくなります。しかし、これはあくまで法律上の話であり、相手が自らの意思で財産分与に応じることを妨げるものではありません。
たとえば、相手が道義的責任を感じていたり、関係を完全に清算したいと考えていたりする場合、話し合いによって財産分与の合意に至る可能性があります。
ただし、法的な請求権がない以上、交渉が難航する場合もあります。相手から「払う義務はない」と突っぱねられればそれで終わってしまいます。また、期間経過後に執拗に要求することは、場合によっては強要罪などと見なされるリスクも伴います。
もしこの方法を試みるのであれば、あくまで「お願い」として行うことになります。また、合意に至った場合は、後日のトラブルを防ぐために、合意内容を記した公正証書などの書面に残しておくのが望ましいでしょう。
3-2 共有名義の不動産などに適用される共有物分割請求とは?
財産分与請求権の2年の期限とは別に、検討できるのが「共有物分割請求」です。
これは、夫婦で共有名義にしている不動産(土地や建物)などがある場合に適用できる可能性があります。財産分与は「夫婦の協力で築いた財産全体」を清算する手続きですが、共有物分割請求は「特定の共有財産」の共有状態を解消するための手続きです。
この共有物分割請求権には、財産分与のような2年の期間制限はありません。
したがって、離婚後2年が経過してしまった後でも、共有名義の不動産が残っていれば、地方裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、その不動産の持ち分に応じた分割(現物分割、代償分割、換価分割など)を求めることができます。
ただし、この方法はあくまで共有名義の財産に限定されるため、預貯金や保険など、他の財産については対象外となる点に注意が必要です。
4 財産分与の合意や審判で確定した権利の時効にも注意!
無事に2年以内に財産分与の話し合いがまとまったり、調停や審判で分与の内容が確定したりした場合も、まだ安心はできません。
ここで確定した「〇〇を支払う」「不動産の名義を移転する」といった個別の請求権には、別途、消滅時効が存在します。
当事者間の合意(協議書・公正証書など)で財産分与が決まった場合、原則として、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で消滅時効が完成します。
一方、調停・審判・裁判で決まった場合は、権利が確定した時から10年で消滅時効が完成します。
たとえば、「1年後に100万円支払う」という合意をしたにもかかわらず、相手が支払ってくれない場合、その支払いを請求する権利は、支払約束日から5年または10年で時効にかかる可能性があります。
この時効は、除斥期間とは異なり、裁判上の請求(訴訟)などを行うことで完成を猶予させたり、更新(中断)させたりすることが可能です。約束が履行されない場合は、早めに法的措置を検討することが必要です。
5 財産分与請求中に相手が財産を隠蔽・移転した場合の対処法
財産分与の話し合いや調停を進めている最中に、相手が財産を不当に減少させる目的で、財産を隠したり、第三者に贈与したりするケースがあります。
このような行為に対しては、「詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)」という権利を行使して対抗できる可能性があります。
詐害行為取消権とは、債務者(財産分与の義務を負う元配偶者)が債権者(財産分与を請求する側)を害することを知りながら行った財産処分行為の効力を、裁判所に訴えることで取り消すことができる制度です。
この権利を行使するためには、①財産分与請求権が具体的に発生していること、②相手方が財産を処分することで無資力(財産が何もなくなる状態)になること、③相手方および財産の譲受人がこちらの権利を害することを知っていたことなどの要件を満たす必要があります。
手続きは複雑で専門的な知識を要するため、財産隠しの疑いがある場合は、早急に弁護士に相談するのが適切です。
6 離婚前に協議を完了させることの重要性と、離婚前の財産分与ができないとされる理由
これまでは離婚後の財産分与請求について解説してきましたが、最も理想的なのは「離婚届を提出する前に」財産分与の協議を完了させ、その内容を離婚協議書や公正証書にまとめておくことです。
離婚後は、相手が話し合いに応じてくれない、連絡が取れなくなるといったケースも少なくありません。離婚という大きな決断をする前に、金銭的な問題をクリアにしておくことにより、精神的な負担を軽減し、その後のトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
「離婚前に財産分与の協議はできても、実際の財産の受け渡しはできない」と言われることがありますが、これは、財産分与請求権が法的に発生するのが「離婚成立後」であるためです。離婚前に協議で財産分与について合意したとしても、その効力が発生するのは離婚届が受理された後になります。
たとえば、離婚前に「預貯金100万円を渡す」と合意しても、その支払いを法的に請求できるのは離婚後です。不動産の名義移転登記なども同様です。しかし、事前に合意書面を作成しておくことで、離婚後速やかにその内容を実現させることが可能になります。
7 離婚前、離婚時どちらの場合でも【弁護士に相談することの必要性】
財産分与は、単に夫婦の財産を半分に分けるという単純な作業ではありません。何が財産分与の対象になるのか、不動産や株式、保険などの財産をどう評価するのかという問題があります。また、相手が財産を隠していないかどうかの調査や、法的に有効な合意書面の作成をする必要があります。相手との交渉や調停への対応もしなければなりません。
これらには専門的な法律知識と実務経験が不可欠です。自分だけで対応しようとすると、本来得られるはずの権利を見逃してしまったり、不利な条件で合意してしまったりするリスクがあります。
弁護士に相談・依頼すれば、相手方との交渉によって生じる精神的負担を軽減できるだけでなく、専門知識に基づき法的に有利な交渉を進めることができます。また、弁護士会照会などの法的な手段を用いて、相手の財産を調査することが可能です。協議、調停、審判、訴訟といった状況に応じた最適な手続きを、迅速かつ正確に進めてもらうこともできます。
離婚と財産分与は、今後の人生を左右する重要な問題です。少しでも不安や疑問があれば、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人DUON法律事務所は、財産分与の実績が豊富で、離婚前離婚後にかかわらず対応することが可能です。財産分与の問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
お一人で判断せずに、離婚に強い弁護士に相談してみませんか?
養育費・婚姻費用・財産分与などのお悩みに、経験豊富な弁護士が対応します。
対面/Zoomどちらも可能。
※ご相談内容により一部有料となる場合があります。